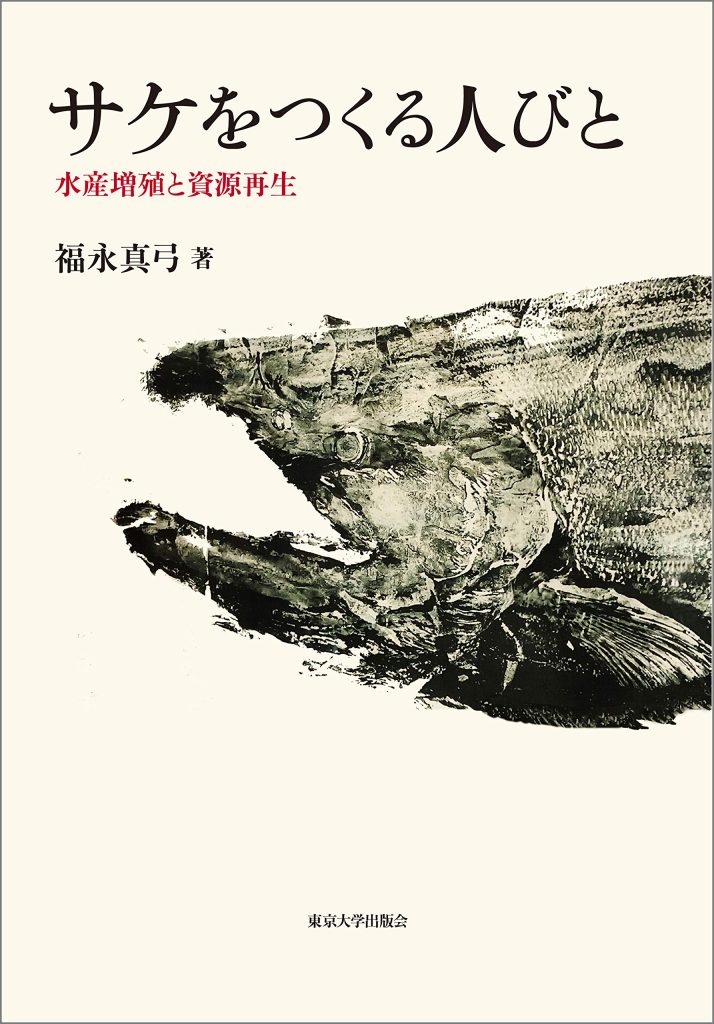近刊紹介『サケをつくる人びと:水産増殖と資源再生』(東大出版会)
2019.12.13書籍・論文
『サケをつくる人びと:水産増殖と資源再生』
著:福永 真弓
ISBN978-4-13-060322-5
発売日:2019年12月10日
判型:A5
ページ数:494頁
サケと人がともに生きる場の再生を目指して――わたしたちの身のまわりにあふれるさまざまなサケ.そのなかで先史時代から日本列島に住む人びとを支えてきたのはシロザケである.「つくられた資源」としてのシロザケの歴史を読み解きながら,「自然」や「野生」とはなにかを問いなおす.
東大出版会
http://www.utp.or.jp/book/b481722.html
内容紹介
主要目次一覧はこちら
主要目次
1.1 「サケ」とはどんな生きものか
わたしたちの食卓とサケ
たくさんのサケ,それぞれの来し方
進行する家魚化とサケ
人新世(Anthropocene)における家畜化と野生化
サケという「つくられた天然資源」
1.2 カワザケと増殖――二つの補助線
カワザケという生きもの
増殖という補助線
人以外が息づく世界を描くための方法論
宮古湾,津軽石川というフィールド
2.1 サケの生態空間を囲い込む
サケを知る,囲い込む
近世中後期の宮古湾とサケ
入会の成立と空間の囲い込み
2.2 境界線を引き直す――サケの生活史の把握と繁殖保護
繁殖保護の始まり
湾内の建網建設に反対する口上書
口上書のなかに見る資源管理と繁殖保護
幕末・明治創成期の漁場と混乱
2.3 サケを「わたしたちのもの」に
3.1 資源増殖という新しい柱
繁殖から増殖へ
増殖概念の歴史的使われ方
3.2 水産行政と人工ふ化放流技術
明治期水産行政の夜明けと米国の人工ふ化放流技術
国家による中央集権型の漁場・水産資源管理の試みと失敗
慣行の権利化と明治漁業法
3.3 繁殖保護から増殖へ
実践理念としての「繁殖保護」の再構成
千歳中央孵化場と人工ふ化放流事業システムの誕生
アイヌ民族と北海道型人工ふ化放流システム
北海道型人工ふ化放流システムの完成
3.4 中央と地方――人工ふ化放流技術の公益性
水産諮問会と増殖の公益性
科学技術の導入と実学としての水産学の形成
4.1 旧慣と入札制
岩手県による漁場統治の形成
県の漁場統治の形成と津軽石
4.2 空間の再所有を目指して
明治初期の漁場入札制度と宮古湾の漁場・資源管理
宮古湾漁業の発展と津軽石村民の漁場からの締め出し
サケガワを取り戻す
4.3 在地型人工ふ化放流システムの形成
津軽石村漁業組合と人工ふ化場の設立
サケ漁の組合自営化
在地型人工ふ化放流システムの形成
5.1 増殖重点化の始まり(大正・昭和初期)
大正・昭和初期の漁業の構造変化
増殖の重点化の始まりと津軽石のサケ漁
人工ふ化放流事業の県営化
5.2 サケのムラの誕生――生活文化の再編成
祭りの再編
物語の再編と祭事
観光のまなざし
5.3 「繁殖保護=増殖」とサケのムラ
6.1 獲る漁業の再生と資源をつくる増殖の重点化
獲る漁業の再生
新しい漁業法と漁業権
獲る漁業の再生と資源の枯渇
獲る遠洋漁業の再開とつくる政策の重点化
サケ・マス資源の母川国主義と縮小する漁場
6.2 獲る漁業と宮古湾
宮古湾から沖合,遠洋へ
浜田漁業部,北の海へ
船頭・前田松雄が語る遠洋
北洋漁業の減退と沿岸への回帰
7.1 政策交渉の道具としての増殖
獲るためのつくる事業
GHQによる批判と提言,新たな科学化
7.2 つくる制度――科学と数
北海道型人工ふ化放流システムの再編と科学化
数を競う事業へ
7.3 数のためのサケをつくる――増殖技術の探求
さけ・ます増殖研究協議会
河川の生産力と環境容量限度の認識
河川省略型技術開発
系統群の選抜
7.4 サケをつくる技術とモノ化の進展
「健やかな魚を,よい時期に放す」
ふ化にかかわる技術開発
健苗育成
適期放流と健苗
親魚の畜養技術
モノ化した生の総合的管理へ
7.5 数をつくるシナリオの拡充――二〇〇海里時代の到来
二〇〇海里体制と制度の更新
受益者負担の原則と沿岸定置網漁業者の主要受益者化
ギンケ増産,消えゆく「カワザケ」
進む家魚化とモノ化
7.6 駆動する増殖レジーム――カワザケからギンケへ
7.7 「わたしたちのモノ」化したサケ
河川省略型技術とサケの生のモノ化
ふ化場の技術者たちの公害・開発へのまなざし
8.1 沿岸の歪みと「つくる」シナリオの必要性
農林漁業基本問題調査会の指摘
つくりそだてる漁業としての栽培漁業
公害への補償としての増養殖
栽培漁業の制度化の始まり
栽培漁業と箱庭型生態系「海洋牧場」
8.2 栽培漁業に含まれる二つの思想
8.3 沿岸における増殖体制の確立
9.1 戦後の津軽石とサケ――在地性の再編成
魚わく海の記憶
在地型人工ふ化放流システムの再開
河口域の保護水面下と空間利用の再編
カワザケと人工ふ化放流事業の再編
9.2 サケは「わたしたちのもの」
10.1 ある津軽石の冬の朝から
10.2 岩手県の増殖レジーム受容
定置網漁業と増殖
内水面から沿岸の生きものへ
10.3 増殖レジームの受容とローカル化
サケをつくる体制の再編
数の増産に向けて編纂される技術と知見
補完技術としての海中飼育
浮上槽とネットリング
未遡上河川にサケを増やす
よい魚を,よい時期に
10.4 去りゆくカワザケ
宮古漁協との合併
技術適用と消えるカワザケ
解体される「わたしたちのサケ」
新たなサケと拡大された在地性の再編
間(あわい)から退出する人とサケ
それでも,カワザケを愉しむ人びと
11.1 何が起こってきたのか――食卓の上の野生化と家魚化
11.2 増殖レジームを再考する
人工ふ化放流技術の属人性とローカル知
触る
つなぐ
読み解き,配置する
直観する
11.3 増殖をサケから再考する――カワザケの再生
増殖レジームの限界と「よい稚魚」
増殖再考
11.4 間(あわい)に身を置くサケ
間(あわい)という領域
モノ化をほどく想像力
11.5 想像から縁を再び結び直す
縁を紡ぐ
再生する
はじめに ※本文冒頭を少しだけご紹介します
海を征服し、その秘密を知ろうとする、すべての者の生活と思想が当然そうあるべき形に、いま海は彼の生活と思想をも形づくりはじめていた。海の広がりと深みのすべてに動きまわる、あらゆる生物に、それがたとえそれが殺す必要のある生物だとしても彼は親近感を持った。しかし、わけても、彼がその運命を支配している大きな海獣に対しては、半ば気恥ずかしく思いながらも、同情と、神秘的ともいえる敬虔な気持ちを覚えるのだった。
アーサー・C・クラーク『海底牧場』(高橋泰邦訳、二〇一三〔一九五七〕)
サケが獲れない。三陸沿岸ではそんな声が東日本大震災のずいぶん前からつぶやかれていた。自営の定置網をもつ三陸の漁協は、「いよいよサケの戻りが悪い」と頭を抱え、町の人は「今年もサケが獲れないらしい」と立ち話をしては、心配そうにハマを見る年が続いた。
これまでサケは、安定的に、かつ量を生む資源管理の成功神話として語られてきた。そのサケが獲れない。しかも魚体が小さい。気候変動の影響に原因を求める声とは別に、サケ資源の安定生産を支えてきた、人工ふ化放流事業の限界を指摘する言葉が、おおっぴらに関係者の口にのぼり始めていた。
東日本大震災後は特に、震災の影響で施設が大きく損傷し、放流数が減少した。
震災前よりもさらに人びとがサケ漁獲の減少を憂えていた、ある春の日のことだ。
わたしはかつてサケ定置網漁船に乗っていた漁師とハマを歩いていた。震災から二年後、まだあちらこちらに津波の爪痕は大きく残されていた。
彼は人生の大半を定置網漁師として過ごしてきた。すでに定置漁船は下りたが、今でもサッパ船でウニやアワビを採りに出る。わたしは彼に会えば、サケと生きてきた彼の来し方を話してくれるようねだる。決して饒舌ではない。はじめはぽつりぽつりと、そのうち、酒が入って興に乗ると、船の上で張り上げていただろう、太い声を響かせて彼は語り始める。
昔は定置網といえばブリだったこと。サケはあまり獲れなくて、地曳網で獲れるサケが楽しみだったこと。一九八〇(昭和五五)年頃にはあふれるようにサケが獲れるようになって、あまりに獲れすぎて天候の悪い日に定置網の船がひっくり返ったこと。今でも毎年、その年はじめて湾にやってくるサケの姿を見るときに心がはやること。
つい先日、放流された稚魚が藻場のなかにいるのをサッパ船から見かけて、つい無事に戻ってこいと声をかけてしまったこと。
もっとも、一番の彼のお気に入りは、幼少期、サケ地曳網の手伝いをしていた兄弟に連れて行かれた浜辺で、網に入ったひときわ大きなサケに睨まれた話だった。南部鼻曲がりとも呼ばれるオスの顔は、睨まれるとそれは恐ろしかろうと思う迫力ある形相だ。
彼の話のなかでは、サケはいつも、睨んだり、つれなくしたり、彼と張り合い、感情を互いに交感できたりする対等な相手として現れる。
「面白いやつだ、サケっていうのは」
あまつさえそんな言い方もする。そして、またサケに睨まれることがありやしないかと楽しみにしながら、変わっていくサケに向き合ってきた。
サケは面白いやつだ。
彼がそういうとき、資源量として換算される数字上のサケとも、タンパク質として消費される切り身になった商品のサケとも、自然保護の対象として象徴化されるサケとも違うサケがそこには居る。人と対等に向き合い、交渉し、敬意すら払われるサケだ。
その彼も、ここのところの不漁にはため息をつく。そして途方に暮れたようにつぶやくのだ。あいつら(サケ)はどこに行ってしまったんだろう、と。
去っていくサケがいれば、新たに現れるサケもいる。
東日本大震災前から、水産庁の増養殖に関する議論を調べたり関係者に話を聞いたりしていると、「サケ・マスもそうだが、栽培漁業の他の魚も含めて、ふ化放流事業にはコスパも科学的にも問題がある」「新しい養殖開発に力を入れた方がいい」「もっと高価格帯の輸出できる魚の養殖を進めたい」という趣旨の発言をよく耳にするようになった。
気候変動により不確実性がさらに増した自然界のなかに、魚を放流して増やそうとするのは効率が悪い。確実に消費者に好まれる高価格帯の魚を、大規模に安定生産できる養殖技術の開発の方が割がよい。そういう思考だ。
実際に世界の魚介類の養殖は近年急激に増加している。一九七二(昭和四七)年の時点では、養殖は世界全体の魚類消費量のわずか七%を占めるだけだった。およそ三〇年後の二〇〇四(平成一六)年には、三九%を占めるようになった(FAO 2016)。養殖は今や水産業の中心になったのだ。
日本でもこの流れにのっとり、技術で「魚」本体を品種改良したり、完全養殖や、海産魚の淡水での養殖化を試みたりと、魚の家畜化、すなわち家魚化が進められている。有名どころでは、マグロやウナギの完全養殖の試みがある。
サケはそのなかでも、世界中で急速に家魚化が進んできた魚でもある。ここ三〇年ほどでその養殖量も増大した。大規模工場式生産技術も実用化され、手頃な値段でサケを食べられるわたしたちの日常を支えている。日本でもご当地サーモンなるものが増え、養殖サケは刺身や寿司ネタにあたりまえの、しかも人気のラインナップになった。
去っていくと漁師が憂うサケと、新たに現れてすでにわたしたちの食卓になじんだ感のある養殖サケ。
はたして、今、わたしたちの目の前に居るサケとは何ものか。
わたしたちは正面からこの疑問に向き合うことも、去りゆくサケと新しく現れたサケがいることに気づくこともなく、ただ商品としてのサケを食べながら変化を受け入れてきた。履歴を語らない商品に囲まれた平生の暮らしのなかでは、人がサケを生きものとしてどのように大きく変えてきたか、変えようとしているか自覚することはない。
そして今、わたしたちが商品に支えられて舌と腹を満たしているうちに、さらにわたしたちの手によって、サケは二つの極へ生きものとしての存在を収斂させられようとしている。人が恐れながら憧れてやまず、人間の領域としての文化と対峙させながら概念化し、生み出してきた「野生」に属する生きものとしてのサケと、生殖過程も形態も肉質も、病気になりやすいかどうかという性質すらも、遺伝子から自在にコントロールして大量に生産し、商品として消費する「家畜」としてのサケだ。
だがそのどちらにも、あの漁師と睨み合うサケの存在は含まれない。
漁師と睨み合ったサケは、人工ふ化放流事業で育ったサケである。人工ふ化放流技術は経済的効率性を追求するため開発された技術手法だ。生殖過程は、育ったら回収することを目的にコントロールされている。捕獲され、形態の選択をされながら人の手によって繁殖し、稚魚期まで飼育される。その意味ではサケは、つくられた資源である。
しかし、育った稚魚は野に放たれる。沿岸から放流されて人の手を離れ、四年から五年を、大洋で過ごす。そして、サケという生きものが歴史的にそうで在り続けたように、母川へ再び繁殖するために戻ってくる。サケはこうして、繁殖への技術介入をその生に組み込んでもなお、生の回遊を変わらずに行って人間の営みに呼応し続けてくれた生きものだ。野生でも家畜でもない間(あわい)―サケと人が互いに働きかけ、応答し、自律性をもってそれぞれの生を営む時空間的広がりと応答そのもの―を長く生きてきた。
この間(あわい)自体は、人工ふ化放流技術によって生み出されたものではない。むしろ、間(あわい)は人工ふ化放流事業が始まるずっと前からのサケと人との長いかかわりのなかで保持されてきたものだ。人びとはサケの生態を理解し、サケののぼる川の空間を所有して地付き資源としてサケを利用してきた。同時に、漁獲制限をして自然繁殖を確保し、産卵場所や稚魚を保護してきた。そしてサケは人びとがサケに働きかける営みを自分の生のなかに組み込みながら、川で生まれ、大洋を泳ぎ、川に戻ることで応答してきた。こうして人と生きもの、その周囲の環境の応答が蓄積されて、野生化でも家畜化でもない間
(あわい)は生まれ、応答の変容とともに少しずつそのありようを変えてきた。
近代になって導入された人工ふ化放流技術は、人間の環境改変と利用増大によるサケ資源の減少をとどめ、効率よく資源を生産するために導入され、開発されてきた。繁殖過程を人の手の元に置き、積極的にサケを「つくる」技術である。養殖技術にも通じる人工ふ化放流技術は、間(あわい)のサケと人のかかわりを変容させつつ、それでもそれまでの歴史的連続性をもつ間(あわい)にサケと人の身を置き続けてきた。
しかし現在、サケが獲れないと憂うる人びとを見れば、何かしらわたしたちは間(あわい)でのサケとの応答に支障を来しているようだ。政策的にはもはや、人工ふ化放流技術は効率性・合理性を失われたとみなされ、人工ふ化放流事業から養殖という極に政策の重心が移されようとしている。間(あわい)から人は退出し、人との応答のなかでその存在を変容してきたサケもまた、家魚化と野生化の両極に存在を収斂させられながら、長くわたしたちと慣れ親しんできた間(あわい)から退出しようとしている。
だが、この間(あわい)からの退出は何を意味するのだろうか。
そもそも、家魚化と野生化の間(あわい)とは、いったいどのようなものだったのだろうか。
間(あわい)にあることがわたしたちにもたらしてきた特別な何かがあるのだろうか。あるとしたらわたしたちは今、家魚化と野生化に向かうなかで、何を手放そうとしているのだろう。
そして、間(あわい)に生きてきたサケとはいったい何ものか。
本書の目的は、間(あわい)に生きてきたサケの存在論的系譜をたどり、間(あわい)における人、モノ、事柄の関係性の履歴をたどることだ。サケと人のあいだに間(あわい)が歴史的に保持されてきた記録をたどり、その間(あわい)でサケがつくられるようになった経緯を、サケをつくってきた、そして現在もつくっている人びとと技術の軌跡とともに追いかける。特に、ここ一〇〇年の変化を生み出してきた、水産行政および研究の主柱である増殖というレジームに着目し、追いかけてみよう。
おそらくこの探求の先には二つの小さな希望が待っている。一つは、間(あわい)だからこそ生み出されてきた、サケと人のかかわりの豊穣さが可能にする、生きものの行く末を生きものとともに想像する力。もう一つは、すでに技術的なハイブリッドな存在となったサケであっても、人びとや他の生きもの、モノに応答し、豊穣なかかわりを生み出す潜在可能性をもちながら、わたしたちとともにこれまでと連続性のある間(あわい)を生み出すことができる、という希望だ。
もう一つの本書の隠れた目的は、この過程を通じて、増殖とともに歩んできた水産学を、増殖のコンセプトが最初に多分に含んでいた重要な概念、人と人以外の生きものの生きる場を再生する学問として編み直すよう提案することにある。
まずは、サケをめぐる旅を始めよう。